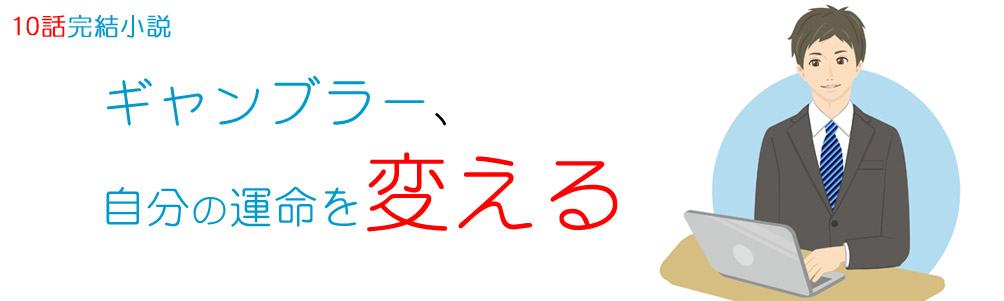どうすればいいのかわからない。
今日は馨の葬式が行われるが、正直そんな精神状態ではない。
あの日、目の前で馨が息を引き取って、僕は何もしてあげられなかった。
抜け殻のようになって、仕事も休みがちになってしまった。
今まで一緒に生きてきた馨が急に居なくなったことによって、僕の人生には大きな穴が開いてしまったような感じだ。
馨の会社の人達が足を運んでくれて、挨拶を交わした。
どうやら部長と課長だけは、馨の病気の事を知らされていたようだ。
僕には心配かけたくないからと話していたことも聞かされた。
だけど、僕は心配かけてほしかった。
いつも僕の方が支えられていたから、こんな時くらい頼られたかった。
結局・・・何も出来なかった。
「水嶋は本当に一生懸命で、よく働いてくれていたよ。
自ら進んで私や部長の仕事も手伝ってくれた」
「俺たちのムードメーカーみたいな奴だったしな。
俺たちの前では決して弱音を吐かなかったし、見せなかった。
あいつは、本当に男らしくて・・・頼もしかった・・」
会社の上司や同僚たちが、泣きそうになりながら話してくれた。
たぶん、一生懸命働いていたのは、残された時間がもう少ないという事を言われたから。
そして、自分が生きている間に自分の借金を返済するためなんだと思う。
あれから気になって、馨の借金について調べたら、ぎりぎりで完済されていた。
また、馨は生命保険に入っていたようで、その保険金が僕宛になっていた。
僕はてっきり喧嘩をしてただ仲直りをしただけだと思っていたが、馨は僕以上に今後の事をちゃんと考えて過ごしていたようだ。
さすが双子の兄だと思う。
ただ、びっくりしたのはこんなにも会社の人達から慕われていたこと。
馨は人見知りだった気がしたけど、意外と社交的だったんだと知った。
「そう言えば、水嶋はお前に彼女が出来たこと、前から知ってたみたいだぞ?
陰ながら応援して気にしてくれていたんだろうな」
「あいつってさ、結構周り見てるし理解してたもんな。
おまけに会議の時、デスクたちともめて自らアイデア採用放棄して困らせてたっけ」
「馨がそんなことを?」
「ああ、病気についてもっと関心を持ち、医療器具を使えるようにしようって。
そうすれば、目の前にある命を救うことが出来るってな」
自分が病気になったことで、関心を持たなければいけないと思ったんだ、きっと。
心臓病とか心筋症だと告げられ、余命まで宣告された時、馨はどう思ったんだろう。
やっぱり、絶望したり泣いたりしたのかな・・・。
馨は僕の前でも涙を滅多に見せたことが無かった。
そんな馨も人知れず泣いていたかと思うと、胸が締め付けられた。
僕に彼女がいることを知っていたのに、あの時何も知らないふりをしていたのか?
それは、僕とケンカをしていたからかもしれない。
陰ながら見守り続けてくれていたことを知らずに、僕は・・・ぼくは・・っ。
「響、泣くなって・・・あいつが悲しむぞ?」
「そうだそうだ!
あいつのために笑ってやれ!」
馨が亡くなった時、僕はずっと子供みたいに泣き崩れていた。
もう会えなくなってしまうのが怖くて、寂しくて。
ずっとくっついて泣いていた。
だけど、馨はとても幸せそうな表情をしながら亡くなっていた。
微笑んでいるかのように、そのまま眠っているかのように。
だから、馨が息を引き取ったと理解するまでに時間がかかった。
今でもひょっこり現れるんじゃないかって、思っている自分がいる。
そんなことありえないと言うのに。
馨・・・僕はどうすればいいんだろう。
ギャンブル依存症は克服したけど、まだ借金の返済が残っている。
それに、友梨佳との付き合いは認めてもらえたが結婚は認めてもらえなかった。
それは、僕が借金をしているから。
このままじゃ、僕はダメになっていくのかな・・・。
「響さん、あの・・・馨さんのお家へ行ってみませんか?
まだ遺品整理していませんよね?」
「ああ、・・・行こうか」
実は、馨の自宅の住所がわからなくて遺品整理にはまだ言っていなかった。
会社の人から住所を教えてもらったから、行ってみることにした。
葬儀を終えて、その足で馨の住んでいた自宅へと車で向かっていく。
車を運転すること約1時間。
馨が住んでいたのは、きれいなマンションでいいところに住んでいた。
借金を返済していたとは思えないくらいのいい部屋だ。
僕は室内へ入り、色々見て回った。
相変わらず、きれいに整理整頓されていて几帳面だったことを知らされた。
家具も最低限しか置かれていないし、掃除も行き届いている。
前もって自分でいらないものを捨てたりしていたのか、ほとんど書類などが無かった。
何か残ってると思っていたけど、何も残っていなかったか・・・。
その時、友梨佳が馨の部屋へ行き、何か見つけたようだ。
「響さん、これ・・・見て」
「どうしたの?」
友梨佳が差し出してきたのは、ある一冊のノートだった。
彼女の話によると、ベッドと壁の隙間に挟まっていたらしい。
そんなところにあったから、馨も気が付かなかったんだと思う。
それは水に濡れてしまったのか、何だか少しだけ傷んでいる。
僕はページを開いて、中身を確認してみることにした。
すると、そこには・・・死ぬまでにしたいことが書かれていた。
箇条書きでたくさん書いてあって、びっくりした。
こんなにやりたいことがあったなんて。
ほとんどが斜線で引かれているから、果たしたんじゃないかと思う。
この3年間近くで、こんなにもたくさんの事をして来たのかと思うと、素直に驚く。
その中には、斜線の引かれていないものが2つあった。
それを見て、思わず僕は涙をこぼしてしまったんだ。
僕につられて友梨佳まで泣き始めてしまった。
「馨・・・どうして・・っ」
「馨さんは、・・・待っていたんですね、きっと」
二人して涙を流しながら、話し合った。
馨がノートに書き記していた言葉を見るたびに、涙が込み上げてくる。
何て言う言葉が残されていたのか・・・それは。
―“馨たちの挙式に出席すること”
―“馨たちの子供を見ること”
そう書かれていて、僕たちは涙が止まらなかった。
この二つだけ斜線が引かれず、そのまま残されていた。
あとは全て斜線が引かれていて、済んだことが分かる。
たったこの二つだけ、果たせなかった。
それは、僕たちがもたついていたからかもしれない。
馨はずっと待っていてくれていたのに、叶えてあげることが出来なかった。
友梨佳が僕の手を強くギュッと握ってきたから、僕も握り返した。
「響さん、もう一度私の両親の元へ挨拶しに行きましょう」
「・・・そうだね、馨はずっと待ってくれていたんだもんな・・。
借金返済して、もう一度改めて挨拶しに行くよ」
「はい、待ってますね」
借金があるからといって、結婚することに反対されている。
だから諦めようかと思ったが、やっぱりそれは間違っている。
借金があるならそれをちゃんと返済して、もう一度挨拶しに行こう。
このノートは持って帰ってもいいだろうか。
これといってとっておく遺品が見当たらないし、このノートは馨が書き残したメモみたいなものだし、筆跡もしっかり残っている。
僕はノートを抱きしめて、体を縮こまらせた。
馨はもうこれから僕のそばにはいてくれない。
笑顔を見ることも出来なければ、もう僕の名前さえ呼んでくれないんだ。
もっと馨と一緒に過ごせばよかった・・・ケンカなんてしないで、一緒に暮らし続けていれば、馨の病気に気が付いたかもしれないのに。
いくら後悔したって、もう遅い。
過ぎた時間が戻る事なんかないのだから。
「ごめんね、かおる・・・っ」
何度謝って意味がないし、遅すぎる。
それでも口にしなければ、自分が許せなかった。
その間にも、友梨佳は僕の手を握ってくれていた。
本当だったら、馨も誰かを好きになって結婚して、子供を作っていたかもしれない。
幸せに過ごせていたかもしれないのに・・・。
運命はいつだって残酷で無慈悲なモノだ。
両親を事故で喪って、今度は馨を病気で喪ってしまった。
僕は独りになってしまった。
―独りじゃないさ、彼女が居る
ふとその瞬間、馨の声が聞こえたような気がした。
そう、だよね・・・僕には彼女が居てくれているし、馨だって僕のそばで見守ってくれているんだよね?
・・・だったら、もう泣かないよ。
辛くて悲しくて、苦しいけど逃げないで頑張る。
だから・・・どうか、僕を見守っていて。
「響さん、そんなに泣いてしまったら馨さんが困ってしまいますよ?
悲しい気持ちは私も痛いくらいわかりますけど、泣かないで」
「友梨佳・・・」
「いつまでも悲しんでいたら、馨さんも成仏できません。
いつでも自分のそばで見守ってくれていると思えば、悲しくありません。
それに、亡くなった人の死は最後のプレゼントなんだと私は思います」
いつまでも僕が悲しんでいたら、確かに馨も心配してしまう。
今度は僕が馨を安心させてあげなきゃいけないんだ。
彼女と一緒にたくましく生きて行く姿を、見せてやりたい。
亡くなった人の死は、最後のプレゼント。
僕には難し過ぎてよく理解できなかった。
死というものは確かに悲しいものだけど、その人が今まで生きてきた証だから、悲しいだけじゃない。
大切な人を喪う痛みや、命の尊さを改めて知ることが出来る。
「響さん、私がそばにいますから」
「・・・ああ、ありがとう」
僕は独りなんかじゃない、だから落ち込む必要なんかない。
今は馨と離れ離れになってしまっているけど、いつか僕もそっちへ行くだろう。
そうしたら、また一緒に過ごすことが出来るかもしれない。
両親も混じって、また家族で過ごせるかもしれない。
そう思うと、少しずつ寂しさが無くなってきた。
これから、僕も頑張らなきゃ。
ノートを再び見てみると、やりたいことリストの中に大きなプリンを食べることとあった。
昔から馨は甘いものが好きで、幼い頃からプリンなどをよく食べていた。
斜線が引かれているから、これも試したという事なんだろうな・・・ははっ、馨らしい。
他にも、いくつか面白いことが書かれていた。
馨らしくて、次第に笑いがこみあげてきた。
「帰ろうか、友梨佳」
「ええ、帰りましょう」
僕は彼女を先に部屋の外へ行かせて、誰も居ない室内を見渡す。
もうこの部屋に来る事は無いだろう。
荷物を片したら、入居者を募集すると大家さんから聞いた。
だから、次ここへ来た時には別人が住んでいる。
「馨、またね」
僕は誰も居ない室内に向かって、そう言った。
さようならは嫌だから、またね、で。