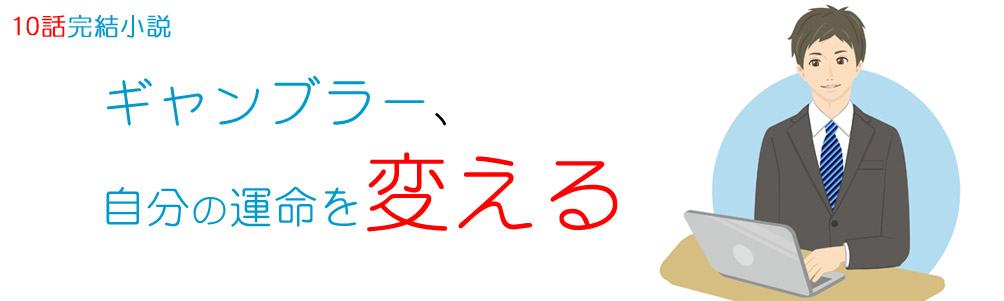毎日患者たちの悩み事を聞いていると、不思議と自分の事を振り返る時間があるような気がする。
自分自身も悩みを抱えていたから、どんな言葉を欲しがっているのか何となくだけれど分かる。
頑張れは一番言ってはいけない、相手の頑張りを否定してしまう言葉。
だけど、少しずつとか無理をせずに、という言葉は相手を安心させ、焦りを無くしてあげることが出来る
一番良くないのは、相手を追いつめて苦しませてしまう事。
俺たち精神科医は出来るだけそうならないよう、ヒアリングをしてアドバイスをし、解決へと導いていくことなんだと思う
患者たちにとって頼れる相手であるべき。
俺の時は、全くと言っていいほど何も力になってくれなかった。
俺は決してあんな医師にはならないと過去に決意して、この職に就いた。
嫌だと思った相手がいるから、良いお手本になってくれて助かっている。
おかげで、俺はああいう医師にはならない。
それに一方的に相手を責めるような言い方も、俺は絶対にしない。
「黒音医師、そろそろお時間になります」
「分かりました」
もうすぐ患者ややってくる。
大きな悩みを小さな体に背負いながらここへ。
俺はその重荷を少しでも軽くしてあげないといけない。
お金をもらって話を聞けていいよな、なんて馬鹿にされないためにも、給料に見合った仕事を、いやそれ以上の仕事をこなしていきたい。
患者が、この人に聞いてもらってよかった、と思ってくれるように。
誰からも人気の医師になろうなんて思わない。
ただ、誰からも信頼されるような医師にはなりたいと思っている。
地位とか名誉とか、そういったものなんか全部俺には必要ない。
それは、自分がきちんと仕事をした暁におまけでついてくるようなもの。
最初から、地位とか名誉にこだわっていたらろくな医師にはならないだろう。
「おはよう、ございます・・・」
すると、診察室に女子高生が入ってきた。
その子の胸元には、痛々しい紫色の痣が残されていて、腕や足にも残されていた。
もしかして・・・虐待?いじめ?
あちこちケガをしていて、痛々しいのが伝わってくる。
俺はどうされました?と女子高生に尋ねた。
彼女は小さな身体を震わせて、口をゆっくりと開いた。
「・・・あたし、人が怖いんです・・ひとが・・・。
虐待、されて・・いじめも・・あたしもう、怖い」
彼女はそう言って、今にも泣きだしそうな表情をしている。
虐待もいじめも経験して、さぞかしその小さな心はズタズタにされてしまっているだろう。
しかし、こうして病院へ来ているという事は、親も一緒なのか?
まさか、一人でここまで来たのか?
酷く怯えているから、何だか心配になった。
このままでは彼女、失神してしまうんじゃないかと思うくらい。
怖いと言う人間が、どうしてここへ来たのか疑問。
そんなことを考えていると、彼女が再びその小さな口を開いた。
「両親は虐待の罪で、捕まって・・・今は施設で・・・。
・・・施設の、ひとがカウンセリング、したほうがいいって、・・・」
「なるほど、それでここへ来てくれたんだね、ありがとう。
君は勇気あるね、怖いと思いつつ今はこうして俺の元へ来てくれているから」
俺は優しく笑みを浮かべながら言った。
それほど恐怖感があると言うのに、施設の人に言われたからと言ってきてくれた。
断っても良かったはずなのに、彼女は自ら一歩踏み出した。
その一歩は彼女にとって、すごく大きなものではないかと俺は思う。
他人から見れば些細なことかもしれないが、俺から見れば大きなもの。
本当は今すぐこんな場所から帰りたいと思っているだろうに。
俺だったら踏み出すまでにもう少し時間がかかる事だろう。
それなのに、彼女は一歩を踏み出した。
それってすごく勇気ある行動。
「勇気、ある・・・?」
「うん、俺はすごく勇気ある行動に思えるよ。
もし、俺が君だったら一歩踏み出すまでに、相当な時間を費やすから。
でも君はためらいつつも来てくれた、それってすごく大きなことだよ」
俺がそう言うと、彼女が小さくはにかむように笑った。
その笑顔は子供のように愛らしくて、かわいかった。
どうして、みんなは彼女の事をいじめているんだろう。
なぜ、虐待なんかしていたんだろうか?
いじめられている側にも少なからずとも原因があるという事は理解している。
しかし、彼女の場合はそれが感じられない。
内気な性格だという事は分かったが、それが連中をいらつかせるのだろうか?
色々つらい経験をして来てしまい、心の時計が止まってしまっている気がする。
先程から、話し方に幼さを感じる。
「黒音医師は・・・親やさしかった?」
「うーん、怒られる時はすごい怒られたし、褒められることってそんなになかったな。
どちらかといえば、良い思い出の方が若干多いくらいで、そこまですごく優しかったわけじゃ・・・」
「・・・・憎いと、思ったこと・・ある?」
唐突過ぎる質問に、俺は思わず黙ってしまった。
自分の親を憎いと思ったことがあるのか?
一度もないと言ったらウソになるけど、だからと言ってそんなに憎んだ事も無い。
確かに俺がやりたいことを阻止された時はいなくなればいいのにって、何度も思ったりした。
だけど、それは子供の頃だけで今はいてくれてよかったって思っている。
子供の頃と言うのは、自分の事で精一杯で周囲が良く見えていない。
だから、どうしても自分中心に物事を考えてしまう。
それなのに、自分が大人になったことで少しずつ余裕が出てきて親が子供っぽく見えることが多くなった。
それは、自分がそれだけ余裕を持てるようになったという事なんじゃないのかな。
「子供の頃はやりたいことを制限されて、そう思ったこともあった。
今は自分が大人になったことで、余裕が出来て親に目が行くようになった。
あの頃口うるさかった両親が、今では少し子供のように見えたりするよ。
君は・・・やっぱり憎いと思っているの?」
「・・・憎いに決まってるじゃん・・。
あたしだって、愛されたい、誰かにちゃんと愛されたいんだよ・・!
虐待するくらいならさ・・・、最初からあたしなんて産まなきゃよかったんだ・・!
どうして、子供は親を選べないの?」
彼女は涙を流しながら、悔しそうに言う。
余程、親を恨み憎んでいることが分かるし、何より彼女が自分自身を嫌っていることが分かった。
両親の事を憎んでいるけれど、彼女が一番嫌っているのは自分自身なんだ。
よく見ると、首には爪で引っ掻いたような痕も残されている。
その傷は、自分で自分を傷つけたのだと一目瞭然だった。
どうして子供は親を選べないの?
その言葉を聞き、俺は胸がとても痛くなった。
確かに、現在ではこんな子供が欲しいとシミュレーションをし、完璧ではないが子供を産むことが出来るようになっている。
それなのに、子供は親を選ぶことが出来ない。
子供が親を選ぶことが出来れば、虐待はどっと減るかもしれない。
「君が一番憎み嫌っているのは・・・・自分だね?
誰かに愛されたいと願うなら、まずは自分自身を愛してあげなければいけないんだ」
「何言ってんの?!
出来るわけないじゃん!!」
「君が嫌っている君を、誰が愛してくれると思う?
自分の味方になってあげられるのは、いつだって自分しかいないんだよ。
自分まで嫌いになってしまったら、誰か自分を守ってあげられるの?」
「・・・・自分の、味方・・?」
「そうだよ、ご家族だっていつかはご病気などでいなくなってしまうかもしれない。
真実が見えなくなってしまった時、自分を守れるのは自分しかいないんだよ。
今すぐ自分を好きになれだなんて、そんなことは言わない。
ただ、ゆっくり時間をかけても構わないから、自分の事を認めてあげよう?
どんなに時間を使ってもいいから、自分を愛してあげられるようになろう」
自分の事を一番よく知っているのは、やっぱり自分なんだ。
自分が諦めて逃げ出してしまったら、自分を守ってくれる人が居なくなってしまう。
それは、とても寂しいことだと思う。
自分が嫌いな自分を愛してくれる人なんていない。
自分の弱さを認めて、すべて受け入れて自分を好きになることが大切。
もしかしたら逆だってある。
誰かに好きだと言ってもらえて、初めて自分の事を好きになれることもある。
どちらにせよ、自分を愛してあげなきゃ可愛そうだ。
時間をかけてもいいから、それだけは諦めないでほしい。
実は、この言葉は俺も言われたことがあるんだ。
姉貴から言われた言葉で、今でもあの時のことを覚えている。
俺がギャンブラーになっていた時、何もかもを否定する俺を無理矢理に抱きしめるのではなく、壊れ物を扱うかのように抱きしめて言ってくれた。
“私はちゃんと柩のこと愛しているから”って何度も言い聞かせるように言ってくれたのを覚えている。
「君にだって君の事を思ってくれている人がいる。
今は信じられないかもしれないけれど、必ず分かるときがくる」
「・・・黒音医師がそう言うなら、信じてみる」
彼女はまだ納得いかない様子だったが、少しでも前を向いてくれたのなら良かった。
午後の診察はこれで終わり。
区切りが良くて俺は、そのまま診察室の外へと出た。
すると、女性看護師たちが集まっているのが見えた。
一体何事かと思い、俺もさりげなく遠くから見ていると若い男性が見えた。
あの顔、どこかで見たことがあるような・・・。
そんなことを考えていると、その男性と眼が合った。
一瞬にらまれたような気がしたけれど、気のせいだろうか?
「君が黒音医師?
今日からここへ赴任した水梨元樹<ミズナシ モトキ>、よろしく」
そう言って彼が手を差し出した。
そうか、握手を求めてくれているのか・・・だったらちゃんと握手しないと。
そう思ってその手を掴もうとした瞬間、さっと手をしまわれてしまった。
・・・・?
「何、気安くオレに触れようとしてんの。
お前と仲良くするわけないじゃん」
いきなり敵意を受けられて、俺はどうしていいのか分からず固まってしまった。
さっきにらまれたような気がしたのは、やっぱり気のせいなんかじゃなかったんだ。
そんなに俺のことが嫌いなんだろうか、初対面で話した事も無いのに。
そして、水梨医師はそのまま女性を連れて去ってしまった。
何も心当たりがなくて、俺はただ立ち尽くすことしか出来なかった。
一体これからどうすればいいんだろうか・・・、