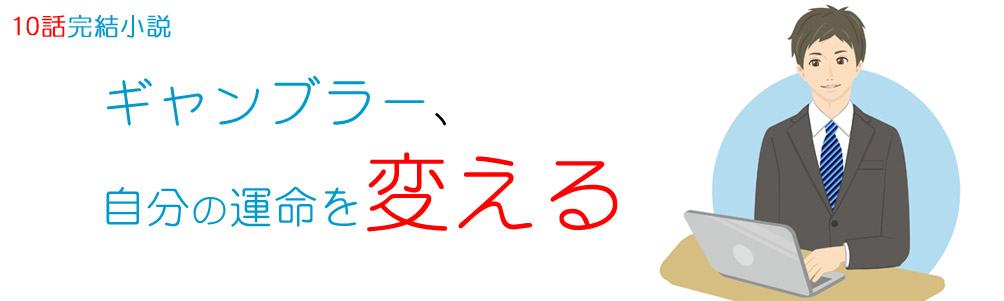――これは今から11年前の話。
俺がまだ25歳の頃に起きた出来事で、あの時は何も解っていなかったんだ。
何を失い、何を得ることが出来たのか。
だけど、今ならよく解る。
さて、俺が何を失い、何を得ることが出来たのか。
読み手の君には解るだろうか?――
俺の名前は三代澤佳晴<ミヨサワ ヨシハル>。
とある商業会社に勤めている普通の会社員で、これと言った特技もない。
どこにでもいるようなごく普通の雇われ社員だ。
別にひねくれているわけでもないし、自虐的な性格と言うわけでもなくそう思っているだけ。
任された仕事は今まできちんと期待に添えることが出来るように頑張ってきた。
それでも昇級への階段の競争率は高い。
俺以外にも上を目指そうとして頑張っている連中はいくらでもいるから。
出来れば俺も上を目指したいけれど、やはりその倍率があまりにも高過ぎてしまって、引け腰になってしまっている。
昇級を目指したいと皆が考えているのは、給料が倍になるからと言う理由もあるし、任せてもらえる仕事が変わるからと言う理由もある。
俺は後者だが、他の連中の多くは前者なのではないかと思う。
「三代澤さん、今月の成果すごいじゃないですか!」
俺に声を掛けてきたのは、後輩である時東楓<トキトウ カエデ>さんだった。
彼女はまだ新入りだが、周囲に溶け込み親しい関係を築き、ムードメーカーとして馴染んでいる。
すっかり馴染んでしまっているから、新入りという感じがしない。
そして、彼女は俺が片想いをしている相手なのだ。
俗に言う一目惚れというやつで、会って少し話をした瞬間、変な話運命を感じたんだ。
普段は運命とか奇跡とか決して信じないけれど、今回はそんな感じがした。
もちろん、まだ自分の気持ちを伝えてはいない。
ただ、彼氏がいない事だけは把握している。
想いを伝えていないのは、フラれてしまう事を俺が酷く恐れているから。
「ありがとう、だけどやっぱり業績トップにはなれなかったよ」
「業績トップは、いつも日向さんですものね!
どうしたらあんなに成果が出せるのかしら・・・」
業績トップは、いつも日向明<ヒナタ アキラ>なのだ。
日向とは同期で、数少ない同僚であるからそれなりに関係を築いていきたかったが、無理だった。
俺は協力しようかと思っていたのに、日向が俺を敵視しているから無理そうだ。
なぜ、そこまで俺を敵視するのかその理由は全く分からない。
業績トップなのはいつもの事だから、周囲ももう驚かなくなった。
ただ、おーっとどよめくくらいで他には何もない。
俺と言えば、いつもナンバー2。
業績トップという壁はまだまだ高くて追い越せそうにない。
遠くにいる日向に目をやると、また女性陣に囲まれていた。
日向は容姿も良いし、業績トップだし仕事も出来るから若い女性陣に人気だ。
それが原因なのか、他の男性陣からはあまり良く思われていない。
「よっ、三代澤!
お前、今月もよく頑張ったよな~」
やってきたのは、俺の先輩である久留宮弓弦<クリミヤ ユヅル>さん。
久留宮先輩も容姿が良いし仕事も出来る頼もしい存在として、男女から支持されている。
何でも知っているから、歩く辞書とも呼ばれている。
久留宮先輩は俺の良き理解者でもあるから、楽しく過ごしている。
いつも俺の事をサポートしてくれるから、非常に心強い。
よく頑張ったと言われて、素直に嬉しさを感じて笑った。
なかなか他人から褒められることなんてないから、素直に嬉しい。
「ありがとうございます。
でも、また業績ナンバー2ですよ?」
「業績がトップになればいいってもんじゃないぞ?
ちゃんと周囲の期待に応えることが出来て、気持ちの良い仕事が出来たかどうかだ。
俺は日向よりお前の方が良い仕事していると思うぞ」
「ありがとう、ございます!」
思わず声が裏返り、久留宮先輩に笑われてしまった。
褒められ慣れていないから、やっぱり変な感じがしてしまう。
それでも嬉しいと思えるから、我ながら素直な方なのではないかと思う。
それぞれの仕事へと戻り、俺は自分がこなすべき仕事に手を付け始めた。
忙しい時はよく残業してきたけれど、ここ最近になってから残業することが無くなった。
それは、俺が時間内に仕事を終わらせることが出来るように、スピードが少しずつ上がってきたからなんじゃないかと思う。
一方、日向はほとんど残業しているところを見たことが無い。
むしろ、残っていた方が珍しい事なのかもしれない。
最近では色々なイベントを準備している。
例えば、多くの人達が動物と触れ合うことが出来るように、期間限定で小さな動物園を作ったり、ペットボトルをリサイクルして何か面白いアイデアを考えたりなど、様々な事業を提案している。
俺たちの会社では、基本的に何かを想像して実現することがメインとなっている。
自分達で考えたことを実現していくことは、とても難しい。
だからこそ、また面白さも出てくるのだと俺は思っている。
「三代澤、ペットボトルの何かいいアイデア浮かんだか?」
「あ、・・・実はいくつか浮かんだんですが・・・。
これと言って特に実現するほどでも無いと言いますか・・・まだ考え中です」
上司に聞かれて俺はノートを見せた。
これといったいいアイデアが浮かばなくて、正直スランプに陥っている。
ペットボトルから作られている物の中から厳選して色々アイデアを絞ってみたが、やっぱり良いアイデアが浮かばない。
すると、上司が俺のノートを見て“おっ!”と驚きの声をあげた。
一体何だろうと思ったら、いきなり俺の目の前にノートを差し出してきた。
それは、ペットボトルの形をした入れ物に入っている折りたたみ傘のアイデアだった。
ペットボトルをリサイクルして傘が作られていることを知って、入れ物を袋ではなくケースにしてしまえばいいんじゃないかと思って書いた、もはやちょっとした落書きのつもりだった。
「コレ、すげーいいじゃん!」
「えっ、これ落書きのつもりだったんですけど・・・」
「ナイス落書き!
コレさ、色々カラーバリエーション豊富にして、ケースのロゴ入れて・・・。
男女兼用で作ったら、ヒットするんじゃないか?」
何も思い浮かばなくて、ちょっとした落書きのつもりがこんなに好感触とは。
とてもびっくりして、俺は思わず上司の顔をまじまじと見つめ返してしまった。
上司は“何てカオしてんだよ!”なんて言って笑っている。
初めて自分のアイデアが採用されたわけではないけれど、久々だったから嬉しかった。
上司と一緒に部長の元へ行き、早速ペットボトルの事業について相談を持ち掛けてみると、部長がすごく気に入ってくれて本格的に始動することになった。
ただ、俺もまだ入社して5年経っていないから、あんまり出しゃばってはいけないような気がするんだ。
出る杭は打たれる、ということわざがあるくらいだし・・・。
しかし、部長が“自信を持ってやれ”と言ってくれたから、少し自信を持ってみようかと思う。
カラーバリエーション豊富というのはいいけれど、どんなカラーにするのかという事で、人気に火がつくかどうか運命が変わってくる。
まず、ブラックは需要があるだろうし、男女兼用ならブルーやピンクがあってもいいと思う。
中間色のグリーンやオレンジもいいかもしれない。
俺はカラーを考えながら、ノートへ書き出していく。
それから、どんなケースにするかというのも大事な部分だよな・・・。
「おいおい、聞いたぞ~!
三代澤のアイデアが採用されたんだってな!
俺にも見せてくれないか?」
「あ、久留宮先輩、お疲れ様です。
ぜひどうぞ、ついでに何かアイデア下さい!」
「俺のアイデア料は高いぞ?」
そう言いながら、久留宮先輩がノートを見てニヤニヤしている。
出来れば、ケースについてのアイデアをもらえると有難いのだけれど、それはワガママだろうか?
久留宮先輩も俺のノートを見て、賛成してくれた。
あまりにも絶賛するものだから、他の上司たちもやってきて少しずつアイデアをくれた。
どんなカラーだったら購入したいと思うのか、どのくらいの価格だったらお手頃なのかとか。
聞けることを出来る限り聞き出して、データに入力して確認してみる。
カラーは全部で7色、価格は2千円未満だったらお手頃というデータが出た。
久留宮先輩が、“ハンドグリップをペットボトルのキャップの部分にあてたらどうだ?”と後押しをしてくれて、それを参考にしてイラストを描き起こしてみた。
それをみんなに見てもらうと“おーっ!”と皆が納得してくれた。
「皆さん、ご協力大変感謝致します!
本当にありがとうございます!」
「いいってことよ!」
「完成したら社割してくれよな~!
ってかするよな?な?」
「あははっ」
皆で笑いながら話していると、部長がやってきてそれぞれの仕事へと戻った。
“賑やかだったようだが何をしていたんだ?”と聞かれて、俺はまとめたデータと描き起こした商品の完成図を部長へ見せた。
ちょっと汚くて見づらいかもしれないけれど、おおよそこんな感じ。
部長が黙り込んでいるから、没にされてしまうかもしれない。
皆からもらったアイデアを参考にして出来上がった完成図とデータ。
俺だけのアイデアではないことも、きちんと部長へ伝えておいた。
自分一人だけの手柄にするのは気分が悪いし、何だか抜け駆けしているみたいで嫌だから。
すると、部長が笑った。
「いいじゃないか、この完成図。
データもしっかりとることが出来ているようだし、その調子で進めなさい。
個人プレーしないのがお前の長所だな。
と言うよりも、個人プレーが出来ないと言った方が正しいか」
「かしこまりました。
やっぱり出来るだけ大人数で協力した方が、良いものが作れると思うんです。
色々なアイデアを混ぜていけば、素敵な結果を生むことが出来ると考えております」
俺がそう真っ直ぐな眼をして告げると、部長はフッと笑みを浮かべて俺の肩をポンと叩いた。
そして、そのまま去って行く部長を見て俺は深々と頭を下げた。
この調子で今後も順調に進めていくことが出来ればいいな。
仕事をするのが面倒だと感じている人が多いけれど、俺はこの仕事にやりがいを感じとても楽しんでいる。
それは色々な事業を起こすことが出来るからなのかもしれない。
色々膨らませたアイデアを実現化して、多くの事を経験することが出来るから。
普通の会社員だったら、ありきたりな毎日というか同じことの繰り返しだから、つまらないとか面倒くさいと感じるのかもしれないな。
そう考えると、俺は自分にとってピッタリな会社に入社することが出来たと思う。
しかし、この時の俺はまだ何も知らなかった。
遠くから日向が俺を冷酷な眼で睨みつけていたという事を。